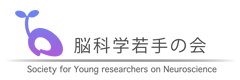この度は「デジタルコンピューターの今後の展望と脳とデジタルコンピューター研究について」と題し、脳科学若手の会 第27回 談話会を開催します。
講師には筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター長/図書館情報メディア系准教授 落合陽一先生をお招きします。
講師:落合陽一先生 (筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター長/図書館情報メディア系准教授)
講師としてお招きする落合陽一先生はデジタル分野での研究者としての活動にとどまらず、アーティストとしての芸術分野での活動もされている実に多才な研究者です。近年、メディアにも頻繁に登場しており、自身のユーチューブチャンネルの開設や情熱大陸、News Zeroなどに出演されています。
今回はそんな落合先生の研究の専門であるデジタルコンピューター研究の今後の展望と我々脳科学に従事する学生向けに脳とデジタルコンピューターについてご講演していただきます。
ご講演はオフラインとオンラインの両方で行います。会場は国立精神・神経医療研究センター内 教育研修棟 ユニバーサルホールです。Zoomでも同時配信いたします。会場参加の方のみ参加費1000円徴収させていただきます。Zoomは無料です。なお学生を優先とした抽選により参加者を選考させていただきます。もちろん社会人の方でも申し込めます。
奮ってご応募ください。
講師:
落合 陽一先生
題目:「デジタルコンピューターの今後の展望と脳とデジタルコンピューター研究について」
要旨:
落合陽一はアーティストとして境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開する一方、技術や文化を探求し続ける研究者でもある彼は、持続可能な社会に向けて作家活動と研究活動の両輪で探索を続けて、政府のデジタル関連の政策委員にも多く関わっています。本講演ではこの10年の計算機と自然化および脳とデジタルについて考えるきっかけを提供することを目的とします。2010年代の後半において計算機科学分野での深層学習の流行をきっかけに、その後の実世界応用までの多くの事例が検証されていきました。その中でどういった応用分野が多くのこるのかということを聴衆と共に考えたいと思います。また最近の取り組みを通じて具体的なシステムなども紹介します。
日時:9月18日(日)
【プログラム】
9:20~9:50 受付
9:50~9:55 開会の挨拶
10:00~11:45 ご講演
11:45~12:00 質疑応答
12:00~12:05 閉会の挨拶
参加申し込み
以下のグーグルフォーム から登録お願いいたします。
締め切り8月12日23:59
お申し込みフォーム
質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
脳科学若手の会:event[at]brainsci.jp
東京大学大学院総合文化研究科・四本研究室との共催で、Yale大学の田中涼介先生をお招きし特別セミナー・座談会を開催いたします。感染対策を実施したうえでの対面開催を予定しております。
セミナー後半では参加者の皆様からも質問を募集して、対面開催を活かした双方向に交流できる機会になればと考えております。どなたでも参加歓迎ですので、関心のある方はお気軽にご参加ください。
日時:8月3日(水) 15時-17時
場所:東京大学駒場キャンパスKOMCEE East K011
*参加無料・事前登録不要
後援者:田中涼介先生 (Yale University)
題目::昆虫の脳でさぐる空間知覚のしくみ
要旨:
われわれの網膜は2次元であるのに、なぜわれわれは空間の3次元構造を視覚的に把握できるのだろうか?空間の知覚の問題は、古くから哲学者や心理学者を悩ませてきた。網膜像から観察者と世界の空間関係を推定するにあたって、とくに視覚的な「動き」が重要な幾何学的手がかりとなることが、環境光学や画像処理の文脈で明らかになっている。その一方で、脳がいかに動きのパターンから空間の情報を読み出しているか、その詳細な神経回路メカニズムには、未だ謎が多い。本講演では、神経回路研究のための遺伝学的・解剖学的ツールが近年急速に整備されつつあるショウジョウバエをモデルに、動きに基づく空間視のメカニズムを探った最近の研究成果を紹介する。
質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
脳科学若手の会:event[at]brainsci.jp
7月19日 (火)の17:30から、今年の11月より理化学研究所で研究室を主催なさる藤原輝史先生のオンラインセミナーを開催いたします。藤原先生は、ショウジョウバエを用いた脳の運動制御機構の研究をされており、本セミナーでは、ハエを用いた研究の魅力や、藤原先生の論文の内容について紹介いただきます。興味、関心のある方はお気軽にご参加ください。
講師:藤原輝史先生 (理化学研究所 白眉チームリーダー 2022/11~)
題目:
ダイナミックな神経活動が操る精密な歩行運動
要旨:
脳の最も基本的な機能の一つは体を自在に動かすことです。私たちは普段歩いているとき体や足の運動を意識しませんが、道には細かな起伏があったり筋肉や神経系の状態は絶えず変化するため、一歩ごとに精密な運動制御が必要です。そのためには視覚や機械感覚といった複数の感覚情報をうまく統合して正確に歩行状態を推定すること、また、その推定をもとに適切な運動指令を生成することが鍵となります。しかし実際に脳がどのようにこうした計算を行っているかはヒトを含めたあらゆる動物種を通じてよく分かっていません。本セミナーでは強力な遺伝子モデルであるショウジョウバエを用いた脳研究における最先端技術を紹介しながら、ハエが運動制御に関する難問の解決のためにいかに適したモデルであるか、また私の研究で明らかになったハエの単一神経細胞の膜電位ダイナミクスに垣間見える予想外に精密な歩行運動の制御機構や今後の研究目標をお伝えできればと思います。
私は本2022年11月より理化学研究所で研究室をオープンします。一緒にエキサイティングなプロジェクトに取り組んでくれるポスドク・博士課程学生を募集中です。
研究室ウェブサイト
7/19 (火)
【プログラム】
17:20〜17:30 開場・接続チェック
17:30〜17:35 開会挨拶
17:35〜19:00 藤原先生のご講演
19:00〜19:30 質疑
19:30頃 閉会
お申し込みフォーム
質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
脳科学若手の会:event[at]brainsci.jp
この度は「免疫から迫る脳」と題し、第13回脳科学若手の会・関西部会セミナーを開催します。
近年では、グリア細胞を始めとした脳内に存在する神経細胞以外の細胞が免疫や脳機能に関与しているという研究結果が多く報告されるようになりました。それにより、今では脳内の免疫機能をさまざまな角度から解明しようとする研究が盛んに行われています。
今回のセミナーでは、脳内の免疫機能について研究されている若手研究者の方をお招きし、その研究の面白さについてお話を伺います。興味、関心がある方ならどなたでもお気軽にご参加ください。
セミナー終了後には講師の先生をお招きし、Zoomのブレイクアウトルーム機能を用いた懇親会を予定しています。途中入退室は自由となっておりますので、こちらもぜひご参加ください。
【講師】
岡崎 朋彦先生(北海道大学 遺伝子病制御研究所・大学院生命科学院 分子細胞生物研究室)
【演題】
「神経と無神経とのあいだ」
【要旨】
脳はこれまでその機能的重要性や、脳と他の器官を隔てている血液脳関門の構造的特徴ゆえに、ミクログリア以外には免疫細胞がほとんどいない免疫特権を有していると長い間考えられてきました。ところが、近年の研究によりこれまで存在しないと思われていたリンパ管 (免疫細胞の通り道)が脳内に存在することや、1細胞解析によって通常の成体の脳内にも様々な免疫細胞が存在することが明らかにされたことをきっかけに神経-免疫相互作用に関する研究が爆発的に加速し、重要な発見が次々とトップジャーナルに報告されています。
今回のセミナーでは、これまで主に「ウイルス感染に対する宿主免疫応答の研究」を行なっていた無神経な私が、どのようなきっかけで神経科学のフィールドに足を踏み入れたか(無神経にも踏み入れようとしているか)について、①これまでの免疫研究の内容と②現在進行中の神経-免疫相互作用研究の内容を交えながらお話しさせて頂きます。
本セミナーを通じて、「病原に対する宿主の洗練された免疫機構」と、それら免疫機構が有する「神経科学におけるゲームチェンジャー」としてのポテンシャルについて皆さんと共有できたらと思います。
詳しく読む
2022年3月12日(土)~13日(日)、第14回脳科学若手の会 春の研究会を開催いたします。感染拡大を防ぐため例年の合宿形式を見送り、研究会として行うことといたしました。講師の先生方をお招きしての講演会やワークショップなど、盛りだくさんの内容です。皆様のご参加をお待ちしております!
なお本合宿は、公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団、及び日本神経回路学会 若手時限研究会の助成のもと開催されます。
| 企業協賛: | 小原医科産業株式会社 |
|---|
| 株式会社ミユキ技研 |
|---|
| 室町機械株式会社 |
|---|
| 株式会社フィジオテック |
|---|
| |
|---|

| 日時: | 2022年3月12日(土)13:00 受付開始~13:30 同13日(日) 9:00~16:00 (予定) |
|---|
| 場所: | オンライン会場(Remo/zoom)で開催致します。 |
|---|
| 定員: | 40名程度(応募者多数の場合は抽選となります。) |
|---|
| 参加費: | 0円 |
|---|
| 申込方法: | こちらよりお申し込み下さい。 |
|---|
| 締め切り: | 2021年2月25日(金)3月4日 (金) |
|---|
| ※2月下旬に抽選結果を連絡いたします。 |
|---|
講演会
- 講師:
- 五十嵐啓 先生
- University of California, Irvine
- 演題:
- 嗅覚から記憶、そしてアルツハイマー病の研究へ / 研究者として生き残る方法
- 要旨:
- TBD
ワークショップ
- 講師:
- 神谷之康 先生
- 京都大学情報学研究科、ATR脳情報研究所
- 題名:
- 実験データ解析再入門―論文を「フェイクニュース」にしないために
- 要旨:
- 概念や仕組みをよく理解しないまま実験データの解析で使っている統計手法はありませんか。神経科学では、大規模で多様なデータ取得が可能となり、統計解析の重要性が増しています。昔なら比較的無害だった統計の誤用が致命的な偽陽性を生み、論文を「フェイクニュース」にしてしまうことがあります。このワークショップでは、実験データ解析で最近よく使われるが授業ではあまり学ばない、効果量、サンプルサイズ設計、多重比較補正、交差検証、混合モデル、ベイズ推論、因果推論などの考え方のキモを、演習を交えて解説します。その後、参加者が作成する実験の事前登録(プレレジ)のサンプルについてディスカッションし、オープンで再現可能な研究実践法を身につけることを目指します。
(過去の合宿のワークショップの様子)



参加についてのQ&A
- Q1. 学部生ですが、参加できますか?
- A1. 是非ご参加下さい。過去の合宿でも学部生のみなさんが参加されています。
- Q2. 今年はポスターセッションは無いのですか?
- A2. Remoで夜間の交流も可能にする予定ですので,その場をご利用ください。
- Q3. プログラミング経験がないですが、ワークショップについていけますか?
- A3. 内容としては大学学部生向けの演習を想定しています。また参加者には、事前に環境構築や初歩的なプログラミングについての資料を配布する予定です。言語はPythonを使用予定です。
参加申込
- 〆切:
- 2021年
2月25日(金)3月4日 (金)
- こちらよりお申し込み下さい。
- お申し込みが完了した場合は自動返信メールがご記入のメールアドレスに送られますので必ずご確認下さい。
- 1時間以内に自動返信メールが届かない場合はお手数ですが再度お申し込み下さい。
- 申し込み者多数の場合には抽選となります。2月下旬に抽選結果を連絡いたします。
その他、ご意見・疑問点などのある方は、こちらまでご連絡ください。
みなさまのご参加をお待ちしております。
脳科学若手の会 合宿スタッフ一同
- 主催:
- 脳科学若手の会
- 日本神経回路学会
- お問い合わせ:
- info@brainsci.jp
Page 3 of 25«12345...1020...»Last »