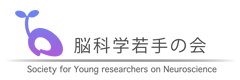CBSでは、2023-2024年にかけて、例年のようにRIKEN CBS Summer Program そして、CBSSセミナーシリーズを開催いたします。
詳細な情報については、下記のWebサイトでご確認ください。
理研CBS Summer Program 2024
CBS Brain Science Seminar Series
*若手の会は、当イベントの運営には関与しておりません。そのため、お問い合わせなどは当該ホームページによろしくお願いいたします。
自然科学研究機構 生理学研究所(生理研)では毎年、全国の若手研究者を対象に生理学研究に関わる様々な実験技術の指導を行っています。第35回となる今年度は全18コースを開講いたします。
参加を希望される方は、以下のウェブサイトを御覧いただいた上でオンラインからお申し込みください。多数のご応募をお待ちしております。
| 開催場所: | 自然科学研究機構 生理学研究所(愛知県岡崎市) |
|---|
| 開催日程: | 2024年7月29日(月)~8月2日(金) |
|---|
| 開催方式: | 現地およびオンライン開催(コースによる) |
|---|
| 参加対象: | 学生および若手研究者、企業研究者 |
|---|
| 参加費用: | 10,700円(アカデミア)・50,000円(企業)
*交通費・宿泊費は含まない |
|---|
| 申込期間: | 2024年5月7日(火)正午 ~ 6月3日(月)正午 |
|---|
| |
|---|
https://www.nips.ac.jp/training/2024/
連絡先
生理科学実験技術トレーニングコース事務局
training2024@nips.ac
*若手の会は、当イベントの運営には関与しておりません。そのため、お問い合わせなどは当該ホームページによろしくお願いいたします。
このイベントは,盛況のうちに終了いたしました。
多くの皆様にご来場いただきまして,誠にありがとうございました。
玉川大学脳科学トレーニングコース2024 -心をくすぐる技の共演-
玉川大学脳科学研究所では、脳科学研究を志す学部学生、大学院生、若手研究者を対象に、研究手法の基礎と応用を実習で学ぶトレーニングコースを開催します。本研究所所属の研究者を講師とし、また本学の研究施設を活用して、脳科学の研究手法の基礎と応用を実習と討論で学びます。
2011年より始まった「脳科学トレーニングコース」は、2020年の中止、2021年のオンラインを挟み中断を余儀なくされましたが、このたび13回目は対面開催とし、通常の講義・実習・議論を行います。本年度から「VRを活用したロボット実験実習コース」を加え6コースとしました。脳科学に興味と意欲を持つ皆さんの積極的なご参加を、心よりお待ち申し上げます。
玉川大学 脳科学トレーニングコース2024
| 日程: | 2024年6月27日(木)〜29日(土) |
|---|
| 会場: | 玉川大学 脳科学研究所 |
|---|
| 対象: | 学部学生・大学院生・若手研究者(文理不問・未経験者歓迎)
※研究室見学ツアーのみの参加も可(定員外/要申込) |
|---|
| 費用: | 受講料3,000円 ※交通費・宿泊費は各自負担 |
|---|
| |
|---|
続きを読む
このイベントは,盛況のうちに終了いたしました。
多くの皆様にご来場いただきまして,誠にありがとうございました。
OISTでは、今年も沖縄計算神経科学コースを6月17日~7月4日に開催します。応募締め切りは1月末日です。ぜひ日本からも多くの若手の皆さんの応募をお待ちしております。
沖縄/OIST計算神経科学コースの目的は、理論系の若手研究者へ神経科学の進展を提供し、実験系の若手研究者に計算モデリングの実践的な体験を提供することです。
この講座は、2024年6月17日から7月4日まで沖縄科学技術大学院大学のセミナーハウスで開催されます。大学院生およびポスドクの参加を募集します。 申込期間は2024 年 1 月 1 日から 1 月 31 日までです。 お申込みはコースWebページからお願いします。
https://groups.oist.jp/ocnc
*若手の会は、当イベントの運営には関与しておりません。そのため、お問い合わせなどは当該ホームページによろしくお願いいたします。
このイベントは,盛況のうちに終了いたしました。
多くの皆様にご来場いただきまして,誠にありがとうございました。
理研一般公開日に、若手7名のPIが大学生・大学院生を対象にラボの紹介(ビデオ)および面談(zoomまたは対面による個別またはグループ)を実施します。現地参加につきましては事前登録制となっております。
*若手の会は、当イベントの運営には関与しておりません。そのため、お問い合わせなどは
こちらにお願いいたします。
現在登録者を募集しています。交流会,研究会,研究員募集などの情報が随時流れます。
メーリングリストの登録と利用規定はこちら
|