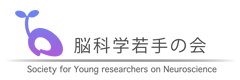2023年3月11日(土)~12日(日)、第15回脳科学若手の会 春の研究会を開催いたします。感染拡大を防ぐため対面とオンラインのハイブリッド形式で行うことといたしました。講師の先生方をお招きしての講演会やワークショップなど、盛りだくさんの内容です。皆様のご参加をお待ちしております!開催場所(対面)東京大学先端科学研究所 4号館2階講堂、(オンライン)Zoom配信
なお研究会は、公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団、及び日本神経回路学会 若手時限研究会の助成のもと開催されます。
| 企業協賛: | 株式会社松尾研究所 |
|---|
| 株式会社ミユキ技研 |
|---|
| 室町機械株式会社 |
|---|
| 株式会社フィジオテック |
|---|
| 小原医科産業株式会社 |
|---|
| |
|---|
詳しく読む
この度は「脳はどこまで再生できるのか〜神経細胞の可塑性に注目して〜」と題し、第14回脳科学若手の会・関西部会セミナーを開催します。
従来の研究では、成熟後の脳内では新たに神経細胞は発生しないと考えられてきました。しかし、近年の研究では、成熟後であってもごく限られた領域で神経細胞が発生していることが分かりました。今回のセミナーでは、脳の可塑性や再生について研究されている研究者の方をお招きし、その研究の面白さについてお話を伺います。興味、関心がある方ならどなたでもお気軽にご参加ください。
セミナー終了後には講師の先生をお招きし、Zoomのブレイクアウトルーム機能を用いた懇親会を予定しています。途中入退室は自由となっておりますので、こちらもぜひご参加ください。
【講師】
金子 奈穂子先生(同志社大学脳科学研究科 病態脳科学分野 神経再生機構部門)
【演題】
「潜在する再生能力を活用した傷害脳の再生」
【要旨】
脳は多数の神経細胞(ニューロン)が作る複雑な神経回路によって、植物機能から思考・学習といった高次機能まで、広範囲にわたる複雑な機能を果たしています。これらのニューロンのほとんどは胎生期に産生されたもので、発達期を終えた脳内では、たとえ疾患や傷害でニューロンを失っても、新しいニューロンを産生して置き換えることはできません。そのため、脳の再生能力は非常に低いことがよく知られています。
しかし近年、成熟した脳内でもごく限られた領域ではニューロンが産生されていることが分かりました。成熟脳で生まれたニューロンは、脳組織内を移動し、神経回路の可塑性や再生に関与します。私達は、新生ニューロンの挙動を制御して脳の再生を促進する研究をしています。
私は大学卒後4年間、精神科の臨床医をしていました。大学院で基礎研究を始めて研究の楽しさを知り、思い切って進路変更しました。基礎研究者としては完全に出遅れており、失敗したり悩んだりすることもありましたが、素晴らしい上司や仲間との出会いがあり、今も大好きな研究を続けられています。
本年4月に同志社大学脳科学研究科の教授になりました。独立にあたってどんなことが役に立ったか、どんなことを後悔したか、など、若手研究者の皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。
詳しく読む
この度は北西卓磨先生オンライン講演会を開催します。
講師には東京大学・大学院総合文化研究科 准教授 北西卓磨先生をお招きします。
講師:北西卓磨先生 (東京大学・大学院総合文化研究科 准教授)
11月25日 (金) の17:00から、2022年3月より東京大学・大学院総合文化研究科で研究室を主催なさっている、北西卓磨先生のオンライン講演会を開催します。北西先生は、げっ歯類で記憶・空間認識の神経回路機構を研究されています。本講演会では、北西先生のこれまでの研究内容に触れながら、海馬の情報処理について教えていただきます。興味、関心のある方は、奮ってご参加ください!
講師:
北西卓磨先生
題目:「領域間情報伝達から海馬の情報処理を読み解く」
要旨:
「いま自分がどこにいて、どこへ向かっているか?」という空間認識は、動物の生存
に重要な脳機能です。海馬には、動物のいる場所・移動スピード・道順などの情報を
持つ神経細胞が存在し、これらが空間認識を構成すると考えられます。しかし、海馬
の情報表現がどのような神経回路メカニズムにより生成され、また、生じた情報がど
の脳領域に伝達されるかは良く分かっていません。私たちは、自由行動中のげっ歯類
の脳に、大規模電気生理計測・多点光遺伝学・経シナプスベクターなどを適用するこ
とで、この課題に取り組んできました。そして、シナプス可塑性が領域間情報伝達を
調整して海馬の場所細胞活動をすばやく生成すること、また、海馬の空間情報は海馬
台を介して複数の下流領域 (側坐核・視床・乳頭体・帯状皮質) へと経路選択的に分配
されることを明らかにしました。こうした研究を紹介するとともに、今後の展望につ
いてお話しします。
私たちの研究室は、2022年3月にスタートした新しいラボです。面白い研究を一緒
に進めてくれる学振特別研究員(PD,RPD)・大学院生・学部生などを随時募集していま
す。
研究室HP
日時:11月25日(金)
【プログラム】
16:50〜17:00 開場・接続チェック
17:00〜17:05 開会挨拶
17:05〜18:30 北西先生のご講演
18:30〜19:00 質疑応答
19:00頃 閉会
参加申し込み
以下のグーグルフォーム から登録お願いいたします。
お申し込みフォーム
質問等、お問い合わせは以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
脳科学若手の会:event[at]brainsci.jp